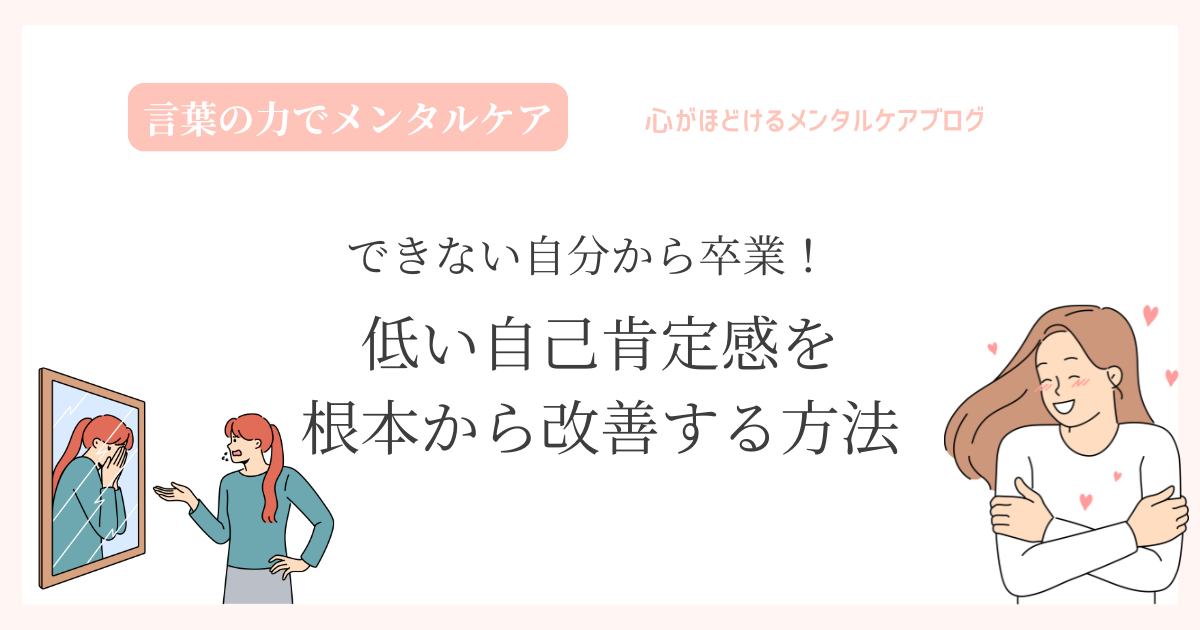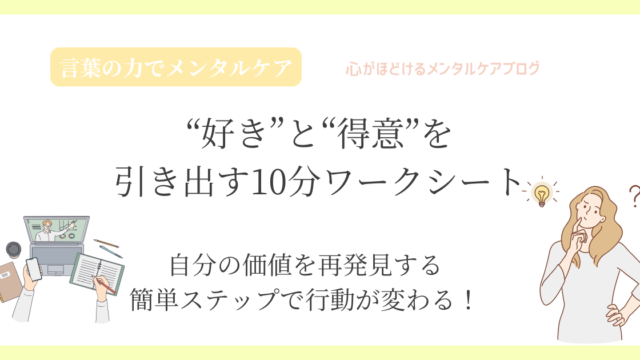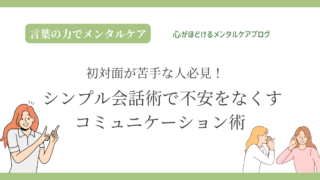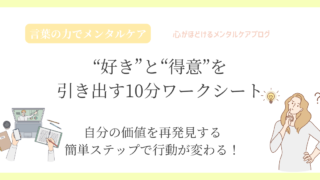できない自分から卒業! 低い自己肯定感を根本から改善する方法
こんな人におすすめ!
-
自分には「できないところ」しか目につかず、いつも自己否定してしまう
-
失敗やミスをすると「やっぱりダメだ」と大きく落ち込む
-
周りと比べて、自分の存在価値がわからない
-
「もっと頑張らなきゃ」と思う一方、頑張ろうとすると心が疲れてしまう
-
自己肯定感を育てて、何事も前向きに取り組みたいけれど、うまくいかない

1. なぜ「できない自分」だと思ってしまう? 低い自己肯定感の背景を知る
1-1. 過去の失敗や批判が強く印象に残っている
人間は、ネガティブな体験を記憶に留めやすい性質があります。過去に大きな失敗や周囲からの厳しい言葉があった場合、**「やっぱり自分はダメだ」「次もまた失敗するんじゃないか」**といった思考が固定化しやすいのです。子どもの頃に親や教師から「できない子」と言われ続けた人も、自己否定感を抱えやすい傾向があります。
1-2. 周囲との比較が当たり前になっている
SNSや職場、学校など、周りには**“できる人”“成果を出している人”がたくさん見えてしまいます。その結果、「自分はあの人みたいにできていない」**と感じ、自己評価を必要以上に低くしてしまうのです。特に完璧主義の人は、例え8割の成功を収めていても、できなかった2割に注目して「またダメだった」と思いがち。
1-3. 自分の努力や成果を認められない思考パターン
頑張っている最中でも「これくらい誰でもやっている」など、自分の頑張りを“当たり前”と捉えてしまう人がいます。少しでもうまくいかなかった部分にフォーカスすることで、結果として「自分はまだまだできない」という印象だけが残ってしまうのです。言い換えれば、「自分を褒める習慣」がないということ。
1-4. 自己肯定感の低さは習慣化される
こうした思考パターンが長く続くと、どんなに努力を重ねても**「どうせやっても無理」「成功したのはたまたま」と否定的に捉えてしまいがちになります。いわゆる“学習性無力感”**に近い状態で、ますます「できない自分」というレッテルを貼るようになってしまうのです。
「自己肯定感を上げるのに特別な才能はいりません。小さな成功や自分を受け入れる習慣を積み重ねるだけで、意外と驚くほど心がラクになりますよ。」
2. “できない自分”から抜け出すための考え方(ゆるめ思考)
2-1. 成功や成果の“ハードル”を下げる
完璧主義で低い自己肯定感に陥る人は、目標を高く設定しすぎて自爆してしまいがちです。7割の達成度を目標に設定して、「ここまでできたからOK」と認める柔らかい思考が必要。
-
例:「英語を完璧にマスターしよう」→「1日1フレーズ覚えるだけでも十分」
-
例:「仕事で大きな成果を出す」→「今日のタスクを定時までに終わらせたらOK」
こうすることで、“できた”実感が増え、自分を肯定しやすくなります。
2-2. “やったこと”に目を向ける(プロセス重視)
低い自己肯定感の人は結果ばかりに注目し、そこに少しでも満足できない部分があると**「できていない」と断じてしまう**傾向があります。むしろ、
-
「今日は30分勉強した」
-
「苦手だった上司に自分の意見を伝えられた」
-
「少しだけど、運動を続けられている」
のように**“やったプロセス”**を重視し、それを自分で認めることで、少しずつ「自分もできることがある」という意識が育っていきます。
2-3. 他人と比較ではなく“自分のペース”を尊重する
SNSや職場で結果を出している他人を目にすると、「あの人と比べて自分は…」と落ち込みがち。ここで気をつけたいのは、“他人の成功”は自分の尺度では測れないということ。
人それぞれ得意不得意があり、ライフステージや環境も違います。他人と比べるのではなく、**「昨日の自分より進歩しているか」**を基準にする方が自己肯定感を保ちやすいのです。
2-4. 自分の優先順位や価値観を明確にする
「できない自分」を感じやすい人は、周りの期待や理想像に縛られすぎていることがあります。そこで、「自分はどうなりたいのか」「何を大事にしたいのか」をはっきりさせるだけで、他人からどう見られるかではなく、自分が納得できる基準で生きられるようになります。
-
例:「人前で話すのが苦手だけど、そこまで無理に得意にならなくてもいいんじゃないか」
-
例:「英語を話せると格好いいと思っていたけど、本当に必要か見直してみる」
自分の価値観を把握すると、「これはそこまで必須じゃない」「ここは頑張りたい」というメリハリをつけやすくなり、「できない自分」へのプレッシャーが和らぎます。
3. 自己肯定感を根本から改善するための具体的アクション
3-1. “できたことノート”を習慣化する
多くの人は「できなかったこと」を数えがちですが、逆に**“できたこと”**を毎日1つでも書く習慣をつけると、自己肯定感が高まりやすいです。たとえば、寝る前にノートやスマホメモで
-
「今日は苦手な資料作成を無事終わらせられた」
-
「上司に意見を伝えられた」
-
「ちょっとだけど運動して汗をかけた」
といった小さな成功を書き留め、「自分も意外とできている」と実感するのです。
3-2. 過去の成功体験を思い出す(反すう日記)
どうしても「できない自分」だと思ってしまう日は、自分が過去にやり遂げたことや、小さな成功体験を思い返してみましょう。**「今までも乗り越えてきたじゃないか」**と再確認できるだけで、現状の問題にも立ち向かいやすくなります。
-
反すう日記:過去に頑張ったことを書き出し、それが自信や実績につながったことを振り返る
3-3. 頑張りすぎない目標を設定し、達成を祝う
仕事や勉強でも、最初から高い目標を掲げるのではなく、**“具体的で小さめの目標”**を設定しましょう。達成したら必ず自分を褒めるのが鉄則。
-
例:1日30分の勉強を1週間続ける
-
例:英単語を1日3つ覚える
-
例:メール返信を溜めずにその日のうちに終わらせる
達成感を積み重ねることで、**「自分にもできる」**という感覚が徐々に育ち、自己肯定感が根本から強くなっていきます。
3-4. 自分へのやさしい言葉を意識する
脳は、自分が発する言葉を思っている以上に受け取っています。**「こんなのもできないなんて最悪」**と口癖のように言っているなら、言葉を変えてみましょう。
-
NG:「やっぱりダメだ…」 → OK:「ここまでできただけでも進歩があったよ」
-
NG:「どうせまた失敗する」 → OK:「もし失敗しても成長のチャンス」
最初は慣れないかもしれませんが、繰り返すうちに脳はその言葉を信じ始め、自己肯定感の土台を作っていきます。
4. まとめ:できない自分から卒業し、“根本”を変えるシンプルステップ
「私はダメだ」という思い込みは、過去の失敗体験や完璧主義、他人との比較など、さまざまな要素から形成されています。だからこそ、**“頑張る方向”**を少し変えるだけで、低い自己肯定感のループから抜け出すことが可能です。
-
完璧を求めすぎず、7割OK思考で“できる自分”を認める
-
成果ではなくプロセスを見て、やった分だけ自分を評価する
-
他人と比べるより、昨日の自分より成長しているかを基準にする
-
自分の欲求や価値観を知り、周囲の期待に振り回されすぎない
-
毎日の小さな成功(できたこと)をメモし、自分を褒める習慣を持つ
このような考え方や行動パターンを習慣化することで、**“できない自分”というレッテルから卒業し、“やればできる”**という確かな自信を積み重ねていくことができます。自分を責めるのをやめて、ゆるめに考えることで、きっと心の余裕やモチベーションが高まり、いろいろなことに前向きに取り組めるようになるはずです。
https://ikirukotoba.com/jikokouteikan_4sen/![]()